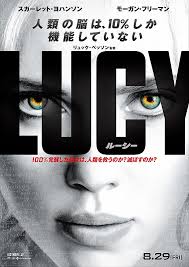iPadやなんかで本を読んでいると、必ず聞かれる質問がある。
「紙の本って、やっぱり電子書籍がはやると廃れるんでしょうかね?」
また、
「電子書籍の時代こそ、紙の本の良さがみなおされるようになりますよね」。
「電子書籍なんて、いっときのブームですよね」までいれると、電子書籍に関して語られるほぼ全ての一般の意見になるだろう。
「電子書籍になってほしい!」という人は、(私のまわりには)あまりいないように感じる。
私は、ぶっちゃけていえば紙の本は廃れる運命だと思う。
重いし、かさばるし、検索に不便。
ある程度の部分までは電子書籍に置き換えられると思うし、そうなってほしいと思う。
その理由を説明したい。
私は、本については情報伝達の一形態だと考えている。
テレビ、ウェブ、ラジオ、新聞なども入れた情報伝達の内の、一つの形態にすぎない。
しかし、その一形態にすぎない本には、人類の知恵が入っている。
私が卒論&修論で取り組んだ思想家イバン・イリイチは、〈本には1ダースもの工夫が2世紀にわたって盛り込まれることで今の形になった〉という。
昔、アルファベットの文章には「スペース」がなかった。つまり、「私は図書館に行きたい」を、「Iwanttogotothelibrary」(I want to go to the library.)としか表現できなかった。
この場合、よっぽど言語力がない限り、なにを言っているか分からない、という状態だった。
「スペース」という「発明」は、本の情報伝達に革命をもたらした。
ページ番号を振る、というのも発明の一つだ。
目次や索引というのも、すごい発明なのである。
人類が本に対し何世紀もかけて取り組んできた成果。それがいまの人類の情報伝達の基盤に成っている。
日本語を見てみても、むかしの日本語にはひらがなの「あ」の表記にも、何通りもの書き方があった。
統一されるのは近代化のあとである。
それまでは無数の「あ」の書き方があったのだ。
「、」や「。」も、古文にはなかった書き方だ。
それまで、「どこで文が終わりか」は、学のある人にしかわからなかった。
明治以降にようやく普及するのがこの「、」や「。」で文を切るやり方である。
それまでは徒弟制度の元、師匠から学ぶしかほかなかった。
もっといえば、お経というものも「ふりがな」した本が当たり前のようにあるのはここ最近のことであろう。
「この文言をどう読むか」というレベルすら、師匠に習う必要があった。
ことふりがなに関してだけでも、人類の発見の歴史が刻まれている。
さて。
本を相手に考えられたこれらの工夫が、ネット時代の今にも役立てられている。
この文章だけでも、「、」も「。」も使っている。
古文になかった「 」(かぎかっこ)や( )すら使っている(古文が難しいのは、「 」が付いていないからでもある)。
人類の情報伝達にかける情熱が、本のさまざまな工夫につながっている。
であれば、本の文化というものは廃れることは永久にない。
電子書籍であれ、ブログの文章であれ、「本」に使われた情報伝達の「知恵」が完全に生かされているのだから・・・。
私はこういう意味で、本はなくならない、と思う。
紙の本に使われた知恵が、電子書籍に活用される。
そういう形での文化の「生き残り」は成立するはずだ。