本日、第2回の「子ども×教育 タベリバ」、開催しました!
今回のテーマは「いろんな人・団体をつなぐ醍醐味」。
教育における外部団体とのコラボの可能性について、
ざっくばらんに話し合いました!
参加者からは「いろんな立場から教育のお話をお聞きできてとてもためになりました」との声を聞かせていただきました。
ご参加頂いた皆さん、ありがとうございます!
次回は1/27(日)、13:00-15:00、
若者協力事業所Link Nextにて開催します!
ぜひ次回もご参加ください☆彡
本日、第2回の「子ども×教育 タベリバ」、開催しました!
今回のテーマは「いろんな人・団体をつなぐ醍醐味」。
教育における外部団体とのコラボの可能性について、
ざっくばらんに話し合いました!
参加者からは「いろんな立場から教育のお話をお聞きできてとてもためになりました」との声を聞かせていただきました。
ご参加頂いた皆さん、ありがとうございます!
次回は1/27(日)、13:00-15:00、
若者協力事業所Link Nextにて開催します!
ぜひ次回もご参加ください☆彡
私がいつも「捨てよう」と思う本がある。
しかし捨てようとしてパラパラ見ると「やっぱやめよう」と思う本がある。
『ぼんやりの時間』(岩波新書)はそんな本の1つ。
どう考えても、「役に立つかどうか」と考えると「役立たない」本。
でも、読むとホッとする本。
筆者は「ぼんやり」を肯定する。
「昼行灯」の大石内蔵助(おおいし・くらのすけ)も
「3年寝太郎」も、ふだん「ぼんやり」する分、
「ここぞ」の大舞台で活躍する。
意味なく「ぼんやり」時を過ごすことが、
人間としてのあり方を回復させる。
そんなテーマの新書である。
どうしようもなく追い込まれた時や、
「この連休、どう過ごそう」と思う時、
『ぼんやりの時間』をパラパラ見ると、
自分が肯定される(電子データではない生身の本にはこんな効能があるのだ)。
映画『のぼうの城』も、「ぼんやり」な主人公が登場する。
普段は農民と田楽踊りに明け暮れ、
武士らしいところが何もない「ぼんやり」な人。
だからこそ「(でく)のぼう様」と呼ばれる。
通常はぼんやりの「のぼう様」だが、
緊急時に強い。
普段の「ぼんやり」や「でくのぼう」性が、
すべて「城を守る」という1点に活かされる。
こういう映画を見ると、人生においての「ムダ」は
「いざ」という時に役立つものだ、と分かる。
この「ムダ」の根源こそ、「ぼんやり」にあるのだろう。
(職業柄、「のぼう様」はADHD傾向があるのではないかと見てしまうが、
それは別の話)。
今日私は定山渓温泉に「ふらっと」行った。
雪を見ながらの露天風呂は非常に旅情を誘う。
『ぼんやりの時間』にはちゃんと「温泉」に1章割かれている。
温泉につかり、何をするでもなくボーっとする。
それが「ぼんやりの時間」。
日常から離脱して「ぼんやりの時間」を取ることで何故かすごく癒された。
「ぼんやりの時間」と「のぼうの城」と「温泉」の三題噺、
以上で幕となります。
本日(2012/11/18)、東京・高円寺コモンズにて、
「「ちょっと変わった学校」を知ろう!」を開催しました!
この企画は私・藤本(日本のノマド・エジュケーション協会 事務局長)と、
伊庭くんとの共同主催です。
フリースクールやデモクラティックスクール、
定時制高校・通信制高校という、
通常の学校とは「ちょっと変わった」学校たち。
その教員によるプレゼンを行いました。
東京シューレ・シューレ大学からは朝倉景樹さん。
定時制高校からは狩野徹さん。
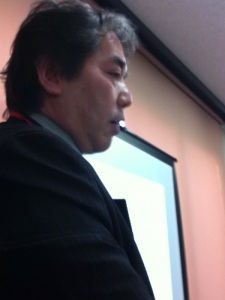
そして通信制高校は私・藤本研一がお話をする、というものです。
参加者からは「充実していました」「もっとお話を聞きたかったです」との、
嬉しいコメントを多数頂戴しました。
また次回のイベントも、実は企画しております。
ぜひまた、お越しくださいませ☆彡
お忙しい中お越しくださった皆さま、
本当にありがとうございました!!!
ちなみに今回、私が一番、勉強させていただきました。
特にフリースクールや通信制高校では、
「お金」がないという問題が大きく現れます。
そんなとき、不遇を嘆くのではなく【生徒とともにカンパを募る】という
いい社会勉強が出来るということを学ばせていただきました。
なお、今回NPO法人カタリバ様には会場提供をはじめ、
多大なご協力を頂いております。
本当にありがとうございます。
本書は、いわば大きな「挑戦の」書である。
つまり、「教員は自分の知らないことを教えることが出来るか」という問いなのだ。
著者・ランシエールの参照する学者・ジャコトによれば「可能だ」という。
ジャコトは自身がオランダ語が分からない中、
オランダ人にフランス語対訳の「テレマックの冒険」という小説を渡す。
学生たちは自分の力でフランス語の読み書きの力をみるみる獲得して「しまう」。
そこからの確信が、ジャコトの「可能だ」という認識につながっている。
「生徒を解放すれば、つまり生徒自身の知性を用いるように強いれば、自分の知らないことを教えられるのだ。教師とは、知性が己自身にとって欠くことのできないものとならなければ出られないような任意の円環に、知性を閉じ込める者なのである。無知な者を解放するには、自分自身が解放されていること、すなわち人間精神の本当の力を自覚していることが必要であり、またそれで十分なのだ。無知な者は、教師が彼にはそれができると信じ、彼が自分の能力を発揮するように強いれば、教師が知らないことを独りで習得できる」(22)
この確信を支えるのが、ジャコトから得たランシエールの人間観である。
「人間は知性を従えた意志である」(77)
ある意味、昔読んだ内田樹の『先生はえらい』に近い。
つまり、「いい教師だからいい教育ができるわけではない」というテーゼを伝えている点だ。
内田の『先生はえらい』は、学ぶ側の思いがあれば、教員の教えていないことすら学習することが出来ることを示している。
ジャック・ランシエールも、ジャコトを通じて伝えているのである。
自分は脅迫的に「物を捨てないと」と思っていた。
それが「シンプル」であり「ノマド」だと感じていた。
しかし、大事なことがようやくわかった。
それは、「自分の好きなもの」をハッキリさせた上で整理する、ということだ。
自分が主催したセミナーに来て下さった講師に教えていただいたことだ。
自分を振り返ると、私は「本」が好きだった。
大学院生時代よりも本は買わなくなったが、それでも「研究者」である以上、本にすごく執着がある。
誠にかわいそうなことに、私の持つ本たち(おそらく数十万ほどは投資している)はダンボールに眠らされていた。
そのへんのゴミやなにかと同じような扱いを受けていた。
これではいけない。
財布へのお札の入れ方で、その人の金運が決まる、という。
非合理的といわれるが、少なくともお札を丁寧に入れる人はお金を細かく丁寧に見ていける人でもあるだろう。
私の本の扱いは、グチャグチャにお札を財布に入れる人と同じだったのだ、と気づく。
本は自分に知のみならず、お金と智慧をもたらしてくれるもの。
ある意味、「お札」以上の存在だ。
だからこそ、本を丁寧に扱う。
粗末に扱わない。
本棚に入れる。
こういった「習慣」こそが、本とのよい出会いをもたらしてくれる。
そんなふうに感じた。
私が高校生のとき、携帯を持っていなかった。
いま、高校生は当り前のように携帯を持っている。
私が高校生のとき、FacebookもTwitterもなかった。
いま高校生どおしがSNSやチーム対戦ゲームで常につながり合っている。
私が思う以上に、高校生を巡る情報の状況は大きく変わっている。
私のようにあまり「気にしない」人間でさえ、Facebookをやり始めた頃、「いいね!」がつかないことにショックを受けた。
高校生であれば特定の相手が「いいね!」をしないことにショックを受けることもあるはずだ。
ではどうすればいいか。
大人でさえ、Facebookで一喜一憂「してしまう」現実を伝えていくことだろう。
少なくとも、「Facebookで傷つくのは自分だけかもしれない」という「誤解」を解決させることが出来るはずである。
本日11/11(日)、「夢が叶う! 仕事がはかどる! 起業家になれる! 部屋の間取りセミナー」を、Coworking Cafe 36にて実施しました!
東京から建築家の方に来て頂き、
一人ひとりの間取りを見つつ実践的なアドバイスをしていくイベントです。
人間、「どんな部屋にいるか」が潜在意識に働きかけます。
だからこそ、「どんな部屋にしたいか」を考え、
すっきりと片付けることが必要です。
「カーテンは外す」
「間仕切りは外す」
「天井照明を外す」などなど、
【居心地のいい】空間にするためのヒントあふれるセミナーでした!
参加して下さった皆さま、ありがとうございます!!!!
アメリカ映画には「監獄もの」が大変多く出てくる。
これは犯罪社会学的に見ると興味深いことだ。
『監獄の誕生』をはじめとして、ロイック・バカンなど現在の「監獄」を巡る議論は多い。「貧しきは監獄に」「民間刑務所」など、アメリカの監獄事情は大きく進化している。
映画でも「ロックアウト」や「マイノリティ・リポート」など、監獄制度を巡るSF映画は近年も多い。
一方、スウェーデンでは犯罪者と住民の「共生」をする監獄もある。
犯罪者が更生できるよう、
アメリカの「重罰化」とは正反対のベクトルに向かっている。
そんな中、アメリカ映画では犯罪者を「隔離」し、「脱獄不可能」にするという制度が大変多く描かれている。
アメリカ映画の描く「未来」は、重罰化・厳罰化の時代となっている。
この方向性の違いはとても興味深いが、アメリカ映画の描く「未来」は、今以上に犯罪者と「普通の」人を隔離する社会となっている。
こういった社会では、一度犯罪を行うと二度と「普通の」人に更生することは出来ない。
しかし、刑務所に入る人間の殆どは軽度な犯罪であることを考えなければならない。
学校にいると、どうしても「サービス」という発想が弱くなってしまう。
これは学校特有の現象かと思っていたが、そうでもないらしい。
本書はフィットネスクラブでのフリーのインストラクターの本。
フィットネスクラブのパーソナルトレーナーには2種類あるという。
1つはフリーランス、もう1つは内部スタッフとしてのアルバイト。
出来高払いのフリーランスのほうが概してモチベーションと能力が高く、「プロ意識」をもっている。
学校の教員とフリーの予備校講師の違いはそこにある。
学校の教員は「教える」のが日常化する。
そこで創意工夫をしてもしなくても、報酬は変わらない(変に工夫することで、組織内評価が大きく下がることもある)。
私は教員でもあるが、(自称)社会学者でもある。
社会学で私が好きなのは「合理的選択論」である。
これは「人間は必ず合理的な選択を取る」、という理論である。
一見「奇妙」な習慣も、元は共同体や個人が利益を得るために行うのだ、と考える理論である。
例えば、未開部族の「雨乞い」を見てみよう。
雨がふるように皆で儀式をすることは「雨」をもたらすこととつながりはないため、「不合理」にみえる。
しかし、雨乞いが必要なほど危機的な干ばつの状況のなか、皆で集まって儀礼をすると、「みなで苦境を乗り越えよう」意識が高まる。
結局は「合理的選択」なのである。
学校経営者は必ず、次のように考えています。
「良い教員を揃えたい」
「良い実践を継続的に行わせたい」
そのためにはどうすればいいのだろうか?
「合理的選択論」的には報酬やモチベーションを適切に提供するシステムが必要なのだ。
報酬とは言っても、お金だけではない。
石田淳がいうように「お菓子」を出すだけでも意味がある。
本書でも筋トレの持続には「目的意識」の明確化が必要だ、という。
そうでなければキツイ筋トレをするモチベーションが低下する。
「合理的選択論」的には、トレーニングをサボるほうが「合理的選択」になるからだ(「楽をしたい」ということだ)。
そうではなく、例えば次のような目標を立てるほうが筋トレの持続性が上がる。
「12月24日までに3kg体重を落としたい」
こんな風に具体的数字・日付を入れた目標を立て、モチベーションを出す工夫が必要なのである。
私は昔ながらの根性論は好きではない。
自分や他者のモチベーションの維持をする方法を、常に自覚的に考え続けること。
それこそ、今後もっとも必要とされるスキルである。
(そしてこれが、今後の教育のテーマでもある)