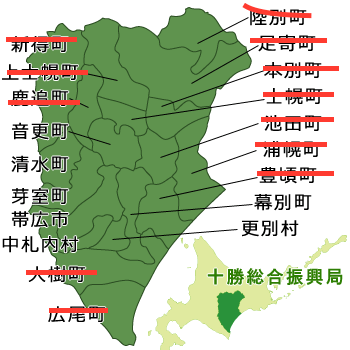2014年 11月 の投稿一覧
心理的サヨナラ主義の考察。
生きることは旅でもある。
その旅の中で、人はひと時他者と出会い、そして別れていく。
寺山修司のいう「心理的サヨナラ主義」は、単なる別れを意味するのではないことに最近ようやく気づいた。
「サヨナラ」と他者に告げることは、別の〈何か〉との出会いのチャンスを広げることにつながる。
私の好きな言葉の一つに「長居は無用」がある。
もはや価値の無くなった場所・組織に長く居ても、自分の成長につなげることは出来ない。
そういう場所・組織に対して、果敢に「サヨナラ」という勇気こそが、次なる成長のチャンスにつながっていく。
「長居は無用」を、私はそんな意味に解釈している。
「長居は無用」。
この言葉から連想されるのは、「長居」がもたらすマイナス面である。
長く居ていいのは、自分との心理的つながりのある場所のみ。
心理的つながりのある場所には、自己を成長させてくれる場所・組織も当てはまる。
「さよなら。」と言えば君の/傷も少しは癒えるだろう?「あいたいよ・・・。」と泣いた声が/今も胸に響いている」
(SMAP「オレンジ」)
この歌の主人公は「サヨナラ」ということで他者の大事さ・他者との関係構築の難しさに気づいている。
言ってしまえば、このことに気づくことだけでも、この出会いに価値があったといえるだろう。
その分自己が成長しているのだから。
↑こちらに収録されていますよ!
こちらもどうぞ!
廃墟のユートピア〜またはグリュック王国に思うこと〜
とかち帯広空港付近の「グリュック王国」は、割と知られた廃墟スポットである。
グリュック王国オープン当初のニュース映像では、〈帯広に中世ドイツの町並みを再現〉という触れ込みだった。
ドイツの祭りの再現や民族衣装など、「ちょっと行ってみたい」感があった。
とかち帯広空港の前を通ると、グリュック王国の塔と観覧車が見える。
買い手や再開発もいまだ決まらない。
ただ廃墟だけがある状態。

皮肉にも、廃墟と化した「中世」の姿を現在の日本に留め続けている。
グリュック王国の存在が持つ哲学的な意味は、「中世」がすでに過ぎ去ったことを象徴的に示している部分である。
廃墟となった建物のオープン当初の様子をVTRで見ると、「ありえた未来」をみるようで切なくも興味深い。
グリュック王国オープン当初のニュース映像が語るのは「懐かしい未来」の姿である。
より活性化する帯広という「未来」をかたどったグリュック王国は、かつての「輝かしい未来」を描いている。
思うのだが、グリュック王国のような地方都市のテーマパークは「作られている」「できつつある」ことのみに意味があるのではないか。
「このテーマパークができると、街が豊かになる」。
そんな「輝かしい未来」を人びとに提供することも目的である。
人は何かが「できつつある」状態に、ワクワク感を抱く。
出来上がってしまうと、「なんだこんなものか」と、失望を招く。
ディズニーランドは毎年新たにアトラクションが増えている。
それと同時に、古くなったアトラクションは撤去されている。
終わらないプロジェクトとしてのディズニーランド。
常に「できつつある」ディズニーランド。
完成することのないディズニーランド。
だからこそ、ディズニーランドは何度行ってもワクワクする。
何度も行きたくなっていく。
考えていくと、このことは人間にも当てはまるように思われる。
常に変化のある人・常に成長しつつある人は見ていて面白い。
人格的に完成した人、というのは一度会うとそれで「もういいや」となりがちである。
(そんなわけで、「変化しつつある主体」(生成変化する主体)としての高校生と接するのは面白い)
いわば「未完のプロジェクト」こそ、テーマパークや人間に求められるものなのであろう。
「未完のプロジェクト」であるべきテーマパークが「完成」してしまうと、もはや廃墟になるしかない。
育ち続ける人・変化し続ける人。
育ち続ける街・変化し続ける街。
「こんなことをやりたい!」
「こんなイベント、やりませんか?」と常に言っている人は「未完のプロジェクト」である分、面白い。
その企画を批判しつづける人はディズニーランドの変化を止めているようで、なんだかつまらない。
「北海道の8割は消えてなくなる?」「その時、十勝は?」(増田寛也ほか『地方消滅』)①
地味に怖い本。
高齢化・少子化を通り越して、〈高齢者も人口減少〉する傾向が現れている日本。
日本は二〇〇八年をピークに人口減少に転じ、これから本格的な人口減少社会に突入する。このまま何も手を打たなければ、二〇一〇年に一億二八〇六万人であった日本の総人口は、|二〇五〇年には九七〇八万人となり、今世紀末の二一〇〇年には四八五九万人と、わずか一〇〇年足らずで現在の約四〇%、明治時代の水準まで減少すると推計されている。(1-2)
二〇一〇年から四〇年までの間に「二〇〜三九歳の女性人口」が五割以下に減少する市区町村数は、現在の推計に比べ大幅に増加し、八九六自治体、全体の四九・八%にものぼる結果となった。実に自治体の約五割は、このままいくと将来急激な人口減少に遭遇するのである。本書では、これら八九六の自治体を「消滅可能性都市」とした。(29)
これ、日本全体的に観た場合に、消滅可能性都市が49.8%となるに過ぎない。
怖いのは、次の部分・・・。
全体の傾向を見ると、北海道・東北地方の八〇%程度、次いで山陰地方の約七五%、四国の約六五%の自治体が「消滅可能性都市」に当てはまる。(30)
なんと、北海道の8割の市町村に「消滅可能性」があるのである!
・・・いろいろ怖い。
なお、北海道十勝管内で「消滅可能性」のある町は次の町(巻末資料より)。
陸別町(若年女性人口変化率-72.8%)
豊頃町(-70.5%)
上士幌町(-67.6%)
士幌町(-65.8%)
浦幌町(-65.5%)
池田町(-65.2%)
新得町(-64.6%)
広尾町(-62.0%)
本別町(-59.3%)
足寄町(-55.7%)
鹿追町(-52.8%)
大樹町(-52.3%)
十勝19市町村のうち、12が消滅した十勝。
下の地図がスッカスカになってしまう。
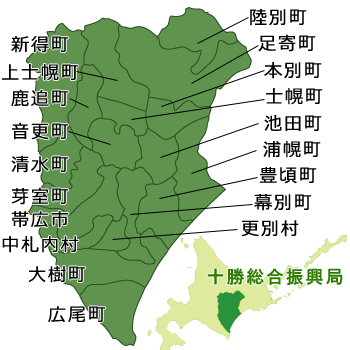
ちなみに、「消滅可能性都市」に斜線を引いてみたのが下の図。
・・・2040年までに何とかせねば、との思いが強くなる。
ちなみに十勝の「村」は「若年女性人口変化率」は-50%を切らないので、消滅可能性都市には上がっていない。
★北海道で一番消滅可能性が高いのは「奥尻町」(-86.7%)です。
大学は何のため?
本日11/8に行った『現代思想』「大学崩壊」の読書会。
かの名高い「現代思想」が「大学崩壊」という現象を探求してしまうとはすごい時代だなあ、と思う。
それくらい、大学が危機なのだというのがなんとなく伝わってくる本。
議論になったのは次のあたり。
●L型(LocalのL.就職予備校化する大学)やG型(GlobalのG. スーパーエリートの大学)の2極化が進むことをどう捉えるか。
(参照https://agora-web.jp/archives/1618134.html)
●大学はそもそも何のためか?別になくても、学べる場所・人と関わる場所があればいいのではないか。
私は「脱学校」論者であるので、「大学はなくてもいい」と思う。
ただ、大学の意義である「学びたいときに学べる場」「誰かと学び、誰かと関われる場」があるのであれば、という条件がつく。
教育社会学でさんざん教育の選別作用などについて学んできたので、「L型/G型」の議論はある意味「昔から言われてきた」ようなこと。
ちょっと前にも「専門職教育用の大学」(これが「専門職大学院」というものに化していった)と「研究用の大学」に分けることは提唱されていた。
しかし真の問題点は、この提言をはねのけていた「教授会」の権限が低下し、「学長のトップダウン改革」(という名の文科省支配)が重視されるようになってきた点にある。
つまり、「現代思想」というまさにG型の研究用大学の人が重視しそうな雑誌の書き手にとって、L型/G型、すなわち就職専門学校化する大学とスーパーエリート大学の2極化が現実になってきているからこそ、脅威に感じられているのであろう。
すでにL型/G型に近い形に大学は2極化している。
いまさら、そのことを批判しようとはしないし、そうなっていくほうが、学生にとっても進路が「見える化」することになる。
(あまりにも高すぎる目標および期待は、人間を駄目にする。三木清『人生論ノート』〈期待は人を押しつぶす〉に近い)
大学、というか高等教育機関の目的は人材の選別・配分にある。
高度な知識・技能が必要とされる職業に、「知識と技能がありそうな」人を送り込む機能である。
大事なのは「知識と技能がありそうな人」を送るという点。
それを見極めるのが「大学卒業」という学歴である。
人間の能力なんて、厳密に図ることは出来ない。
「血を見るのが苦手」な人が医学部に受かってしまい、たまたま医師国家試験に受かってしまうこともある。それで専門が「外科医」になる場合、「知識と技能」はあっても適性はない。
そういうこともある。
しかし、大体の場合うまくいく。
そういう制度が、社会では要求されるのである。
これ、教育社会学の「常識」なのだが、「それって、教育じゃないじゃん」という批判をモロに浴びる分野である。
大体の人は、大学というものに必要以上に幻想を持っている。
真理の探求や学友という存在、『三四郎』的な初恋、などなど。
けれど、そのいずれもが「別に大学じゃなくてカルチャーセンターでもいいんじゃないの」という問いに答えることはできないものだ。
だから「大学じゃなくてもいいんじゃないの?」と思ってしまう。
『現代思想』2014年10月号特集「大学崩壊」に思うこと。
本日11/8(土)、毎月やっている読書会で『現代思想』という雑誌の「大学崩壊」特集号を元に議論を行います。
それにあたってのメモを。
・・・・・・・・・・・・・
・いろんな議論が出ているが、主になっているのは次の3つ。
①「国立大学法人化と、学長のトップダウン強化によって大学が自主性を失い、文部科学省ないし政府の意向をただ伝えるだけの組織になっている」
②「グローバル化が叫ばれ、新たな部局を作成する大学増えているが、その中身は「外国人教員を~~人雇う」レベルの対応となっており、それで問題が解決するのか。またそもそもその対応で正しいのか」
③「非常勤講師の雇い止めなど、非常勤講師をめぐる勤務状況は厳しくなっている。専任の教員との間の待遇差が広がっている」
これら①~③から考えて、「改めて、本来、大学はどうあるべきか」の問い直しの必要性を本書は訴えている。
まず考えるべきことは、大学のあり方は進学率など社会状況によって変わる、という点である。
マーチン・トロウは大学をエリート段階・マス段階・ユニバーサル段階の3段階に立てわける(『高学歴社会の大学』)。
進学率15%までのエリート段階、50%までのマス段階、それ以上のユニバーサル段階だ。
日本は現在「ユニバーサル段階」に到達している。
いわゆる、「大衆教育社会」(苅谷剛彦)だ。
それぞれの段階に応じて、大学に求められるものは変わっていく。
人類はエリート段階での大学にだいぶ慣れ親しんできた。
それが戦後しばらくでマス段階(大学紛争の際言われた「マスプロ教育」とは、この段階のときのことである)に達する。
60年代の大学紛争。
安田講堂に立てこもったのは 現代史の教科書に載っている出来事だ。
現代史の教科書に載っている出来事だ。
その当事者たちが感じていた思い。
「大学に入るともっと学問の自由を謳歌できると思ったのに、数百人一度に教えるマスプロ教育と、卒業後すぐに「企業戦士」となる未来しか描けない」
「けっきょくは日本という社会の中の歯車にしか過ぎない自分自身」
このような彼らの満たされない思いが、マルクスの洗礼で火炎瓶なり、歩道の敷板を剥がしての戦いなり、大学封鎖なりにつながっていった。
彼らの不幸は、大学がすでにマス段階に達しているのにもかかわらず、彼ら自身の思いが「エリート段階」の大学が担っていたものであったことがそもそもの原因である。
一対一で教授と学生が共に学問をし、
世情のことを無視して象牙の塔にこもってひたすら思索できた時代。
そんなものは幻想なのだが、「エリート段階」の大学の理想はそこにあった。
日露戦争勃発を知らなかった帝国大学教授がいた、という話など、まさに古き良き象牙の塔の時代の話である。
マス段階の大学に進学した、大学紛争当事者たちは、大学に「エリート段階」の幻影を求めていたのである。
そんなものはすでに時代遅れになっているにもかかわらず。
さて。
大学の役割は「マス段階」から、進学率50%突破の「ユニバーサル段階」に達した。
大学だけで見れば、それは2002年ごろ。
割と最近、日本の大学は「ユニバーサル段階」に達している。
いまの日本の大学を巡る状況は、大学関係者以外はいまだマス段階の発想でもある。
大学紛争当事者の悩み同様、そこが今の日本の大学の不幸をもたらしている。
例えば。
(1)「大学入学は厳しいから、もっと個人を評価するシステムにすべきだ」という言説。
いまや日本の大学はAO入試や推薦入試で6割もの学生が合格する。
筆記試験で合格を果たす学生は少数派になりつつある。
これもマス段階の発想である。
(2)「大学院に入り、脇目もふらずに研究に励めばそのうち専任講師や助教授・教授になれる」という言説。
これもマス段階の発想である。
10年前に比べ、大学院修士課程に進学する学生数は2倍になった。
しかし、大学での勤め先の数はほとんど変わっていない。
非常勤講師の待遇も悪くなったほか、大学院生が「つなぎで仕事する」場所の定番だった専門学校や予備校も、少子化のため減少している(東進ハイスクールのように、DVD授業をする予備校も増えているし)。
だから脇目もふらずに研究に励んでも、「よっぽど」でなければ、専任講師にも助教授にもなれないという時代が来ている。
なれたとしても、それは研究職を期待されてのポストではなく、「生徒の就職指導ができる」「教育実習のための指導・援助ができる」「学生支援ができる」、挙句の果ては「バスが運転できる」ということだけを期待されての仕事口であったりもする。
私が博士課程進学を断念し、通信制高校教諭の道を選んだのも、「こんな」理由がある。
ただ、教職という進路は職にあぶれた大学院卒業生たちの流れる「社会的受け皿」でもある。
教育的熱意を持たない大学院生がデモシカ教員になっていないかが不安な限りである。
このように、大学に関するすべての不幸の始まりはマス段階・ユニバーサル段階であることを無視して議論をするところから起きているのだというのが私の仮説である。
一度、その発想からいまの大学に関する言説を洗いなおし、「現象学」的まなざしで検討を重ねることが必要であろう。