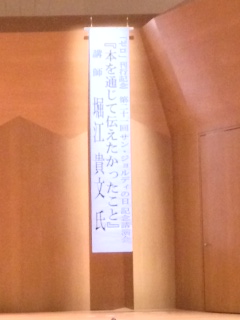佐藤学といえば、言わずと知れた「学びの共同体」の提唱者。
本書はその「学びの共同体」が「手っ取り早くわかってしまう」本である。
宮台真司から社会学の世界に入った私にとって、〈折り合いの付かない他者とも一緒に学ばなければならない「学びの共同体」なんて、絶対いやだ〉と思っていた。
「学びの共同体」を、「学(まなぶ)の共同体」と揶揄していた時期もある(当然、「佐藤学」の下の名前を意味する)。
しかし。
『学びをつむぐ』の著者・金子先生との出会いがイメージを変えた。
金子先生は埼玉の公立高校で「地歴」「公民」を教えている。
方法は「学びの共同体」を用いる。
金子先生は授業の際、机を「コ」の字型に移動させ、教卓を横にずらすところからはじめている。
「コ」の字にするのは〈生徒同士の声を聴き合うため〉、教卓を横にずらすのは〈教員の権力性を排するため〉。
(…教卓を横にズラすことについては、私も教員になって以来、マネさせてもらっている。教卓を挟まずに生徒と話すと、なんというか「臨場感」が増す気がするのだ。教卓」の分だけ、生徒と距離がある気がするのである。)
金子先生がこんなことをするのは、教員-生徒間、生徒同士が「聴き合う」関係を結ぶためだ。
つまり、学びを「個人が教材と向かう」営みでなく、「他者の声を聴き合い、考える」営みと捉えることからはじまっているのである。
この「聴き合う」関係こそ、「学びの共同体」の目指す姿である。
(余談だが、金子先生の授業を見たことで、〈こんな自然体で授業ってできるんだ〉と気付き、〈自分も、授業ができるかも〉と考えるようになった。それが大学院生だった私を「教員」の道に引き入れることになった)
はてさて。
本文に移ろう。
本書は日本の教育の問題とその特殊性をついた前半と、「ではどうするか」を述べる後半にわかれる。
斜に構える人物の多い教育社会学の文献と違い、佐藤学の本からは「教育とはなにか」を一生懸命考えよう、という姿勢が感じられる。
大学院生時代はその一生懸命さが「幼さ(ナイーブさ)」であるように感じられたが、教員をやると「この人はやっぱ、日本の教育をよくすることに必死なんだな」と感嘆の思いで読むようになった。
佐藤は日本の教育の根本問題について、次のように述べる。
〈「民主主義」と「公共性」の危機こそ、今日の日本の社会が陥っている最大の危機であり、教育危機を生み出している中核的な問題と考えるからである。〉(ⅷ)
「民主主義」とは、要は「聴き合う」関係が日本の教育に少ないことにつながる。
「公共性」は公教育の専門職性が足りない、ということの指摘につながる。
〈子どもたちに求められているものは「ゆとり」ではなく、教育内容のレベル・ダウンでもなく、学びの意味の復権と学びの快楽であり、勉強から学びへの転換である〉(16)
うん、「学びの意味の復権と学びの快楽」。
授業でやってみたいもんだ
(なかなかできていない…反省)。
佐藤学の「学びの共同体」は社会民主主義的な側面を持つ。
〈学校が学校としての機能を再生するためには、「教養の伝承(リテラシー)」と「民主主義(デモクラシー)」と「共同体(コミュニティ)」の三つのキャノン(規範)が復権されなければならない〉(68)
〈社会民主主義の教育改革は、多様な人々が互いの差異を尊重し合って共生する民主主義の社会を展望し、これまで国家が管理してきた教育の公共圏を地域を基盤とする共同体のセクターへと移譲し、学びのネットワークを基礎として学校の三つのキャノンを復権する改革へと向かっている。「学びの共同体」づくりとしての教育改革の展開である〉(69)
では改革の具体例に移ろう。
〈教室の改革においてもっとも重要な課題は「一斉授業か個人学習か」にあるのではなく、中間領域の小グループの「協同学習」にある〉(101)
「無理やり」を意味する「勉強」から、自分の興味・関心を広げ、主体的な営みである「学び」へ転換することを、佐藤は重視する。
〈教室のコミュニケーションの基本は聴き合う関係である。学びは一般に主体的で能動的な行為として語られがちだが、むしろ心と身体を開いて他者の声を「聴く」という受動的な感覚に根ざした「受動的能動性」として性格づけられる行為である。教室でいくら「はい」「はい」と手があがって活発な意見が出ようとも、その子どもたちが教師や他の子どもの言葉に耳をすまし合う関わりを築いていなければ、自らを変容させるような学びを体験することはないだろう〉(109)
〈「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。今問題なのは「依存」も「自立」もできない子ども、すなわち人と関わることが苦手な子どもが増えていることにある〉(108) 〈ボランティア活動や文化・スポーツ活動を通して市民社会に参加する機会が、子どもや若者に豊富に準備される必要がある。大人の意味ある活動に参加したとき、子どもと若者は大きく成長することができる〉(171-172)
まさに「参加(participation)による学習」である(「正統的周辺参加」だ)。
子どもが他者と関わり「社会」とつながることを重視した教育活動である。
それこそが「学びの共同体」の最終的な理想像であろう。
…まったく「どうでもいい」ことだが、この本のラストはとてもグッとくる。
〈一人でもできることはたくさんある。私自身の経験をふりかえっても、これまで二〇年間、毎週二校から三校の学校を訪問して学校を内側から改革する実践に協力してきたが、学校を訪問するときはいつも一人であった。どんな組織にもどんな人にも依存しない一人の歩みだった。その一人の一歩一歩がいくつもの出会いを生み出し、改革のネットワークを形成してきた。いや、私を含む一人ひとりが一人でもできることをつなぎ合わせたからこそ、出会いの連鎖が生まれ改革のネットワークが形成されたのである〉(194)
まさしく「ノマド」な姿である。
わがノマド・エジュケーション協会も、こうありたいもんだ。
〈今、教育に求められているのは、一人ひとりが当事者として遂行する小さな挑戦の積み重ねである〉(199)