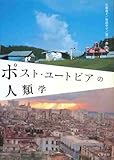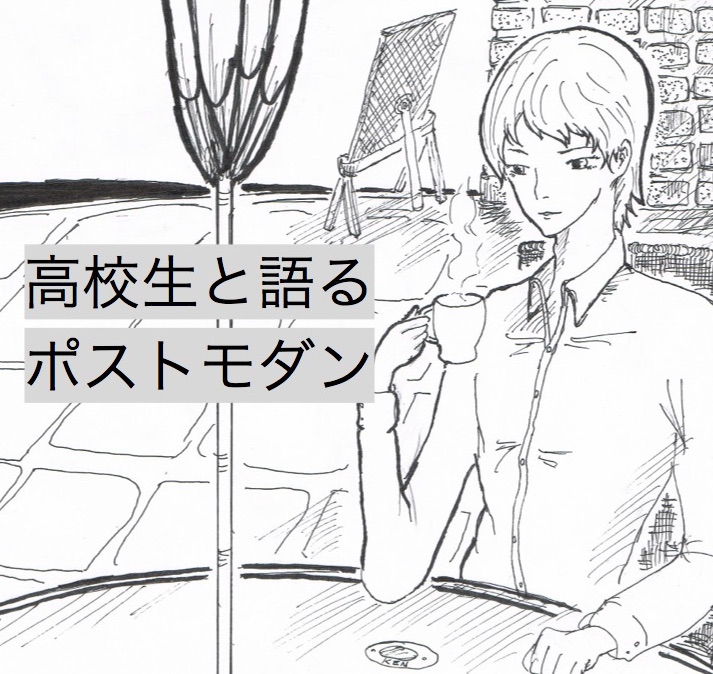とかち帯広空港付近の「グリュック王国」は、割と知られた廃墟スポットである。
グリュック王国オープン当初のニュース映像では、〈帯広に中世ドイツの町並みを再現〉という触れ込みだった。
ドイツの祭りの再現や民族衣装など、「ちょっと行ってみたい」感があった。
とかち帯広空港の前を通ると、グリュック王国の塔と観覧車が見える。
買い手や再開発もいまだ決まらない。
ただ廃墟だけがある状態。

皮肉にも、廃墟と化した「中世」の姿を現在の日本に留め続けている。
グリュック王国の存在が持つ哲学的な意味は、「中世」がすでに過ぎ去ったことを象徴的に示している部分である。
廃墟となった建物のオープン当初の様子をVTRで見ると、「ありえた未来」をみるようで切なくも興味深い。
グリュック王国オープン当初のニュース映像が語るのは「懐かしい未来」の姿である。
より活性化する帯広という「未来」をかたどったグリュック王国は、かつての「輝かしい未来」を描いている。
思うのだが、グリュック王国のような地方都市のテーマパークは「作られている」「できつつある」ことのみに意味があるのではないか。
「このテーマパークができると、街が豊かになる」。
そんな「輝かしい未来」を人びとに提供することも目的である。
人は何かが「できつつある」状態に、ワクワク感を抱く。
出来上がってしまうと、「なんだこんなものか」と、失望を招く。
ディズニーランドは毎年新たにアトラクションが増えている。
それと同時に、古くなったアトラクションは撤去されている。
終わらないプロジェクトとしてのディズニーランド。
常に「できつつある」ディズニーランド。
完成することのないディズニーランド。
だからこそ、ディズニーランドは何度行ってもワクワクする。
何度も行きたくなっていく。
考えていくと、このことは人間にも当てはまるように思われる。
常に変化のある人・常に成長しつつある人は見ていて面白い。
人格的に完成した人、というのは一度会うとそれで「もういいや」となりがちである。
(そんなわけで、「変化しつつある主体」(生成変化する主体)としての高校生と接するのは面白い)
いわば「未完のプロジェクト」こそ、テーマパークや人間に求められるものなのであろう。
「未完のプロジェクト」であるべきテーマパークが「完成」してしまうと、もはや廃墟になるしかない。
育ち続ける人・変化し続ける人。
育ち続ける街・変化し続ける街。
「こんなことをやりたい!」
「こんなイベント、やりませんか?」と常に言っている人は「未完のプロジェクト」である分、面白い。
その企画を批判しつづける人はディズニーランドの変化を止めているようで、なんだかつまらない。