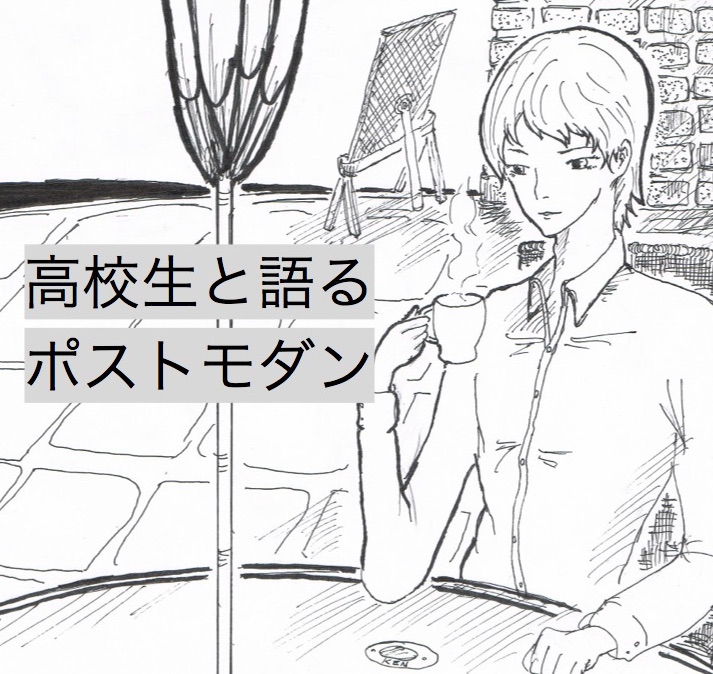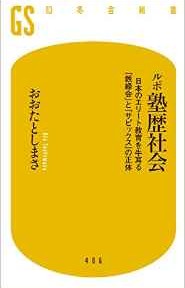
前の記事の続きです。
前の記事はこちら!
本書『ルポ塾歴社会』では、【サピックス小学部→鉄緑会】というコースをたどった人たちへのインタビュー記事が前半部分を占めます。
このインタビュー記事の部分。
なんというか・・・。
前回も書いたとおり、
「いまいちピンとこない・・・」感満載です。
それは私が「中学受験って、なんですか?」という片田舎に育ったことも大きいです。
どうも「首都圏の子どもは大変だなあ・・・」という思いを持つ本でした。
「大学に入るまで塾に頼り切る生き方は、もしかしたら私から、何かを深く思考する能力を奪ったのかもしれないとおもうことがあります。もともとそういうことがニガテだったのかもしれませんが、そのことに目を向けず、お山の大将に慣れてしまうシステムなのかもしれません。そういう生き方が向いている人も必ずいるわけですから、それが一概に悪いことだとも言えませんが」(45)
(桜蔭→東大文Ⅰ→東大ロースクール→弁護士の女性へのインタビュー)
小学生のうちは、目標の学校に入るためにどれだけの学力が必要で、そのためにどれだけの努力をしなければいけないのかなど、子供本人がわかるはずもない。塾の指導に右向け右になることはやむを得ない。しかし、それが強烈な成功体験として刻まれ、中学・高校生になっても塾に頼り切りになってしまうと、主体的な学習習慣を身につける機会が奪われてしまうのかもしれない。(45-46)
そして、【サピックス小学部→鉄緑会】という黄金ルート日本のエリート教育をある意味「固定化」「制度化」させてしまう危険があることを本書『ルポ塾歴社会』は危惧しています。
その一つが〈サピックス小学部のほうが、名門中学校の入試問題に対し「こんな設問をしている限り、うちの塾からはその中学校への進学を勧められない」というクレームが入る〉とということかもしれません。
ただ、本来的に塾は「学校で足りないこと」「学校でできないこと」を補う働きをしてきています。
塾の生徒からも、「学校の授業はつまらない。だけど、友だちと遊べるから学校に行っている」という言葉を聞くことがあります。
「塾のほうがわかりやすい」という声も聞きますし、
「これって、こういう意味だったんだ!」という素朴な感動を、
塾で授業をしていて共有することもあります。
学校とは別に塾という学びの場があることで、子供たちは自分に合う学習スタイルを見つけたり、より多角的な刺激を受けたりできるのである。
「学校歴×塾歴」で、教育のバリエーションが無数に増える。日本の学校制度が平等で画一的であったからこそ、教育の多様性をもたらすために、塾という「変数」が自然発生したようにも私には見える。(146)
その意味で、塾と学校は決して敵対しないもの。
同じ子どもを、違う立場からサポートしていけるものなのです。
逆に言えば現在は、塾があるからこそ、学校は学校でいられる。目先の大学合格だけでなく、生徒一人ひとりの人生の20年後、30年後をも見据えた本質的な教育に力を注ぐことができる。だから学校の多様性も担保される。その意味で、塾は学校教育を陰で支えるパートナーなのだ。(144)
かつて、札幌で塾を運営する能正章寛さんという人は「塾は学校と地域・家庭の究極の裏方」という名言を述べていました(いまも述べています)。
教育という点で、子どもを「究極の裏方」としてサポートしていけるのが塾である、という観点です。
本書を読んで再確認した気がします。
公教育が「与えられた教育」であるとするならば、民間教育は「自ら求める教育」と言える。その2つがあることで、日本の教育は常にバランスを保ち、かつ、柔軟に進化し続けることができた。これは世界でもまれに見るハイブリッドな教育システムなのである。(145)
札幌で新たに作文教室ゆうをはじめる者として、「世界でもまれに見るハイブリッドな教育システム」を支える一員になりたい、と思っています。
さて、この『塾歴社会』を元に、4/9(土)に読書会を開催します。
【Facebookイベントページ】『ルポ塾歴社会』読書会
4/9(土)22:00-23:00、会場は札幌市営地下鉄「幌平橋駅」徒歩5分の
【個別学習塾はる】です。
ぜひ本書片手に語り合いませんか?
ご参加お待ちしています!
(参加希望の方はこちらからご連絡ください)
おおたとしまさ, 2016, 『ルポ塾歴社会 日本のエリート教育を牛耳る「鉄緑会」と「サピックス」の正体』(幻冬舎新書)。
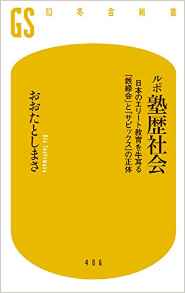 ☆こちらからお求め頂けます。
☆こちらからお求め頂けます。