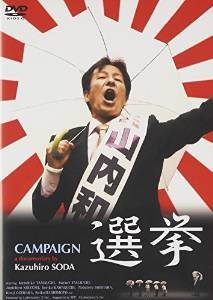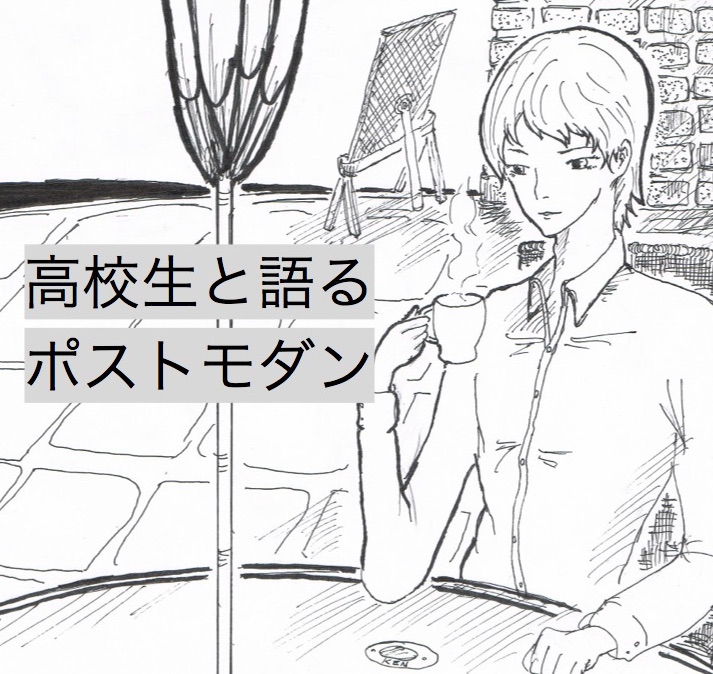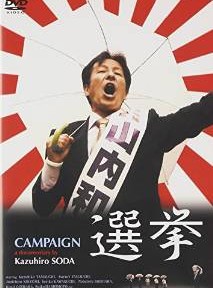
〜大平亮介さんのFBからの記事です〜
ラジオを聴いて勉強になったので書きます。
地方議会のあり方についての話です。
■地方議員の不祥事はチェック不足から生じる
市民団体やNPOなどによるチェックがある自治体は議員の不祥事が生じにくい。
なぜならば明らかにおかしなことはおかしいと指摘されると、嫌でも襟を正さざるを得ないからです。
指摘を放置すれば次の選挙に落選する可能性が高まるからです。
■限られた人だけが立候補する
昔は、各業界の利益団体が自分の組織から利益代表を議会に送り込み、応援するという構造がありました。
今はどの利益代表にもコミットしないという有権者が増えている。
しかし、どの団体にもコミットしない代表がいない。
なぜならば、議会は平日の昼間に開会され、仕事をしているサラリーマンは議員になりにくいからです。
そうすると、平日の昼間に議場に行ける職業の人しか議員になれないという実態があります。
議員になれる人の人材が限られるので、立候補する人が少なく、いつも決まった人しか立候補しなくなる。
その結果、どんどん有権者の関心が下がり、投票率の低下にもつながるのです。
■ごく一部が得する選挙の構造
有権者の関心が下がれば下がるほど、自分たちの利益代表を出して、得をしている人たちの存在が大きくなります。
逆説的にいうと有権者が関心をもたなければ特定の人だけの権限や利益が増えていくのです。
一部の人たちの関心は高まり、その人たちの投票率は高くなります。
つまり組織票の割合の比率がどんどん上がるのです。
そうすると組織がない人はなかなか選挙に勝てない、しかも仕事を辞めて立候補しようと考える候補者は限られる。
こうした選挙の構造はできるだけ得をしている人にとってはブラックボックス化して動かしたくなくなってしまいます。
地方議会での選挙のあり方、考えたいものです。
【藤本追記】
地方での「選挙」の実態については、これがいい「参考文献」になりますよ〜↓!